35年住宅ローンを組んでいる私は、ローン残債2,200万円を抱える会社員ですが、借入先である銀行からの「返済予定表」では、借入利率が0.15%UP。毎月の返済金利が約2,000円上昇していました。
2025年1月、日銀の利上げは2024年7月の利上げに続き25bp引き上げられ、政策金利は0.5%となりました。金利上昇、固定VS変動、物価高。インフレ時代に突入した、住宅事情のニューノーマルをお届けします。
住宅ローンの変動金利は、短期プライムレートに依存します。
””短期プライムレート(たんきプライムレート)””とは、銀行が企業などの優良な取引先に対して短期間(通常は1年未満)で貸し出す際の最優遇金利のことです。
特徴
• 主に短期貸出に適用される(例:手形貸付や短期融資)。
• 一般的に、日銀の金融政策や市場金利の影響を受けて変動する。
• 長期プライムレート(1年以上の長期貸出向けの優遇金利)とは異なる。
政策金利とは?
””政策金利(せいさくきんり)””とは、中央銀行(日本では日本銀行)が金融政策の一環として設定する基準金利のことです。この金利を操作することで、景気の調整や物価の安定を図ります。
日本における政策金利
日本銀行が設定する代表的な政策金利には、以下のようなものがあります。
① 無担保コール翌日物金利(誘導目標)
• 現在の実質的な政策金利で、金融機関同士が短期間(翌日まで)で資金を貸し借りする際の金利を日銀が調整します。
• 日銀が金利を下げる → 企業の借入コストが下がる → 景気を刺激
• 日銀が金利を上げる → 借入コストが上がる → 景気を引き締める
② 日銀当座預金の金利
変動金利とは?
変動金利とは、融資期間中の適用金利を半年毎に見直す貸付方法です。
変動金利のメリットは、固定金利に比べて、契約開始時点で安い金利で借りられる事です。
反対にデメリットとして、総返済額の見通しが不透明ということです。融資期間中に「利上げ」が行われれば、返済総額は増えることになります。
昨年7月の利上げに続き、今年1月の利上げがされ、そろそろ住宅ローンの変動金利にも影響が出てくる頃として、世間では不安視する声が大きくなっているように感じます。
例:変動金利0.6%、固定金利2.1%で4,000万円のローンを組んだ場合の初年度返済シュミレーション
変動金利:年間24万円、2万円/月の金利を返済することになります。
固定金利:年間84万円、7万円/月の金利を返済することになります。
利上げ発生!毎月の金利負担は2,000円増加
住宅ローンを契約すると、「返済予定表」というハガキが半年に一回郵送されてきます。
この返済予定表で確認しなければならないのが、「適用金利」と「払込利息」です。
残りのローン残高と適用金利を元に算出された、払込元金と払込利息の内訳と、総額の「払込元利金」が記載されています。
筆者の2025年1月作成の返済予定表では、適用金利が0.625%から0.775%に上昇していました。
払込利息は毎月約2,000円上昇しました。
住宅ローンの5年ルールと125%ルール
5年ルール
前述の払込元利金は5年間据え置きです。適用金利が上昇しても、毎月返済額はすぐに値上げされません。これは日銀の利上げ発表で、すぐに家計圧迫をしないように設定された措置ですが、6年目には契約期間でローンが完済できるように、改めて毎月返済額(払込元利金)が決定されます。つまり、利上げにより毎月返済額が上がるのは、適用金利の上昇から6年目となります。
125%ルール
6年目の毎月返済額は、5年目までの金額の125%が上限となります。これも急激な金利上昇から債務者を守るルールです。
注意点として、この5年ルール、125%ルールは元利金等返済にのみ適用されます。
契約時点で元金均等返済を選んでいる場合、適用されません。
金利上昇対策
繰り上げ返済
毎月の返済とは別に、まとまった金額を返済する方法です。借入金額が大きく減るので、支払う利息を低減させることができます。
繰り上げ返済は、最低金額や手数料が金融期間ごとに設けられている場合があるので、事前に確認しましょう。
例:借入金額2,000万円、借入利率1%の場合
2,000万円✖️1%=20万円(毎月約16,666円の利払い)
↓500万円を繰り上げ返済した場合
1,500万円✖️1%=15万円(毎月12,500円の利払い)
繰り上げ返済を行う場合には、「借入期間短縮」と「毎月返済額の減額」を選択できますが、借入期間短縮を選んだケースの方が、総返済額は安く済みます。
しかし、例題で挙げたケースで言えば、金利返済だけでも4,000円の低減効果があります。返済金額減額パターンを選択すれば、毎月の可処分所得を大きく確保できます。ライフサイクルや家計の状況に合わせて選択することをお勧めします。
借り換え
現在融資を受けている金融期間より、低い利率で他の金融期間から、借り直すことができれば毎月の負担や総返済額を抑えられるかもしれません。
注意点としては、手数料がかかるので、一時的に大きな出費となります。総額で借り換え効果が有効なのか、検討しましょう。
モゲチェックを利用すれば、金融機関の適用金利を一括で見積もり可能です。
住み替え
住み替えには、売却、賃貸化の2通りがあります。
また、自身がこれから住むべき住居を検討する必要があります。
一般に、支払いが高額で生活にゆとりがなくなってきた、と感じているのであれば、住居費は最低でも2割程度下げたいものです。
収入UP
差し迫った脅威では無いとしても、給料アップの可能性があるのであれば、昇進試験や社内手当が出る資格取得などに取り組みましょう。
収入アップし、生活水準を上げなければ貯蓄が増やせるはずです。ゆとりある収支は将来の利上げ対策に有効です。収入>固定費➕変動費なので、安心して暮らせるでしょう。更なる利上げがあったとしても、今まで蓄えた貯蓄で当面対応可能です。
賃金アップの方法が思い当たらなければ、副業を始める事で収入アップすることもできます。
住宅売却で残債割れが地獄
残りの私の残債は2,200万円です。
仮に今、自宅を売却したとして、売値が2,000万円だったとしましょう。
2,200万ー2,000万=➖200万円です。
自宅を売却し、住むところが無くなるのに借金が残る。これが残債割れです。
これは避けなければならない状況です。
自宅を高く売るには?
① 売却のタイミングを見極める
不動産市場は時期によって価格が変動します。
• 需要が高まる時期を狙う
• 一般的に 1~3月、9~11月 は住宅購入者が増える時期(新生活・転勤シーズン)。
• 金利が低い時期や不動産価格が上昇傾向にある時も狙い目。
• 金利や政策の影響を考慮する
• 住宅ローン金利が低いと買い手が増え、価格が上がりやすい。
③ 適正な価格設定をする
• 査定を複数の不動産会社に依頼する
• 1社だけでなく、複数社に査定を依頼して相場を把握。
• 「一括査定サイト」を活用すると便利。
• 強気すぎる価格設定は避ける
• 相場より高すぎると売れ残り、結果的に値下げを迫られることも。
• 類似物件の価格を調べる
• 近隣の売出し価格や成約価格を参考にする。
⑤ 信頼できる不動産会社を選ぶ
• 実績のある不動産会社に依頼
• 口コミや評判を調べ、売却実績のある会社を選ぶ。
• 「大手 vs 地元業者」→ どちらが得意なエリアかで選ぶのがコツ!
• 媒介契約の種類を選ぶ
• 専属専任媒介契約 → 1社のみだが手厚いサポートあり。
• 専任媒介契約 → 1社のみだが、自分で買い手を見つけることも可。
• 一般媒介契約 → 複数社に依頼できるが、手厚いサポートが受けにくい。
売却方法 特徴
仲介(一般的な売却) 高く売れる可能性があるが、時間がかかる
買取(不動産会社に売却) 早く売れるが、相場より安くなる
リースバック(売却後も住める) 売却後も賃貸として住み続けられる
これから家を買う人へ
オーバーローンを避ける。これに尽きます。
住宅ローンは、業績の安定した優良企業に勤めていれば、年収のおよそ8倍まで借りられる(目安)と言われています。2020年頃までは超低金利時代と言われていたので、誰も金利上昇を気にせず、多くの人が変動金利で借入を行なっていました。
金利が安いから、なるべく多く借りて、カッコイイ家に住みたい。これが消費者の意見で、銀行もこれに笑顔で対応していました。
しかし、日本にも金利上昇の波がやってきたのが2024年です。多くの人が一斉に金利、住宅ローンを気にし始めました。
銀行の思惑としては、以下の様相です。
- 大きい金額を融資したい
- なるべく金利を取りたい
- 貸し倒れは避けたい
家は買って終わりではありません。その後数十年という生活があります。
住宅ローンを組みたいと思って銀行に行っても、
- 家族構成、ライフプラン
- 1馬力?2馬力?
- 家計収支
これらの事は銀行に質問されません。銀行が確認するのは、与信評価(勤め先、世帯年収、借金など)のみです。子供が生まれたり、仕事を辞める事情がある事など気にも留めません。それは、物件という担保があるからです。(返せないなら担保を引き上げます。というのが銀行の考えです)
ローンを組む前に、パートナーがいる場合はライフプランと生活費についてよく考えるべきです。
金利上昇、管理費、修繕積立金の上昇などで、悩むことになるのはローン債務者である皆さんです。
住宅ローンを年収の5倍目安とすることで、不動産市況の下落、金利上昇に備えることができます。また、住居費は収入の25%以内にするとリスクを減らせると言われています。
これから金利は上がる?
景気、物価が上がれば金利は上がる。悲観的思想が高まれば金利は上がる。不況になれば金利は下がる。金利とは基本的にはこういうものです。
4月の日銀政策決定会合の利上げは見送られる観測ですが、その先はまだわかりません。トランプ関税により、世界的に株価は暴落し、不安定な値動きとなっています。
90日間の追加関税停止という決定はありましたが、既知の通り発動されれば、消費意欲低下、企業業績悪化は免られません。企業の業績悪化は労働者の賃金や賞与にも影響します。この環境下になる可能性があるうちは日銀も中々利上げに踏み切ることはできないでしょう。
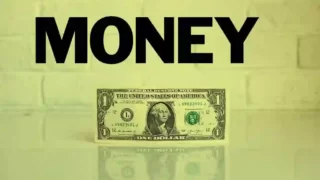

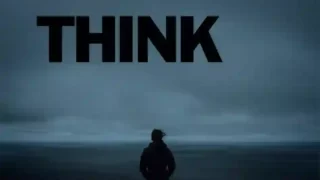
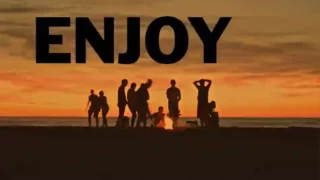



コメント